1400〜1500年頃
ルネサンス:
この言葉は知らないと恥ずかしいかも。 でも意味を知ってる人は少ない。意味は、「復興」「芸術復興」。何を復興させたか。古代ギリシャ・ローマ時代の精神を復興させた。このことを作品を見て分かる人は少ない・・・。昨今は、「ダウィンチコード」がブーム。
レオナルド・ダ・ヴィンチ
今やだれでも知っている。作品は「モナリザ」と「最後の晩餐」が超有名。「ダウィンチコード」をあなたは、読みました?観ました?
|
 レオナルド・ダ・ヴィンチ「最後の晩餐」(部分)
レオナルド・ダ・ヴィンチ「最後の晩餐」(部分)
クリックすると拡大(修復後)で見られます |
|
<物足りない人のために・・・>
「最後の晩餐」はどこかの美術館にあるのではない。壁画として、ミラノにある「サンタ・マリア・デレ・グラツィエ教会」という所にある。大きさは約4×9メートル。予約制で見ることが可能。99年5月に20年にわたる修復が終わり、それまでイエスは口を閉ざしていたと思われていたのが、実は口を開いていたとか、マタイのヒゲは汚れだったことなどが判明した。
なお、個人的見解としては、「ダウィンチコード」は、あくまでミステリー小説であり、美術史そのものに影響を及ぼすものではないと思います。
1600〜1700年頃
バロック:
上の、ルネサンスに対して、「風変わりな」という意味が「バロック」。ルネサンスの整った美に対して、激しさが加わります。ここで、覚えたい画家は、
エル・グレコ
スペインの画家。幻想的な宗教画を描く。 |
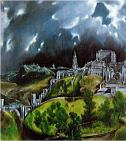
エル・グレコ「トレドの風景」(部分)
クリックすると、この絵がある
メトロポリタン美術館に入れます。 |
<物足りない人のために・・・>
グレコくらいになると、今日では買うことは到底無理。代表作の「受胎告知」が倉敷の大原美術館にあるが、これは、創設者の当時「倉敷紡績」社長、大原孫三郎が戦前入手したもの。実際に購入したのは、依頼された画家の児島虎二郎。孫三郎の執念は、城山三郎の小説にもなっている。ちなみに「倉敷紡績」とは、今日のクラレのこと。クラレは、日本の美術界に大きな貢献をしていたことになります。
|
 モネ「睡蓮」(部分)
モネ「睡蓮」(部分)
クリックすると睡蓮がたくさんある、マルモッタン
美術館に入れます。 |
1800〜1900年頃
印象派:
印象派という呼び名くらい、誰でも聞いたことはあるだろう。キーワードは光。
画家はいっぱいいるけど今回は・・・
クロード・モネ
モネだよ、モネ。同じ画家でマネという人がいるけど間違えないで。
|
|
<物足りない人のために・・・>
「印象派」という呼び名は、モネが若い頃に出品した「印象―日の出」という作品名から、後にそう呼ばれるようになったもの。モネは晩年になると池の睡蓮に情熱を持ち、何と200点に及ぶ同じテーマでの作品を制作した。日本ではいくつかの美術館に所蔵されているが、代表的なものが、上野の「国立西洋美術館」にある名品だ。
|
1900〜1950年頃
シュールレアリスム:
よく「シュール」なんて言うよね。意味は超現実主義のこと。言葉の意味を論理的考えると頭が変になりそう。画家としては、この人が特に有名。
サルバドール・ダリ
ぐにゃぐにゃした時計とか。特徴的な作品で見れば大体分かる。映画や著作もある。 |
 ダリ「記憶の固執」(部分)
ダリ「記憶の固執」(部分)
クリックすると、ダリ美術館に入れます |
<物足りない人のために・・・>
シュールレアリスムという言葉は、アンドレ・ブルトンという作家が、1924年に発表した「シュールレアリスム宣言」から生まれた。「夢と現実が、超現実の中に解消する」といった内容で、日本でも翻訳本が出ている。なおダリの版画がたまに売られているが、欲しい人は、本人のサイン入りか、もしくは本人が死んだ後、関係者の入れたサインか、よく確認して買うべし。もちろん前者のほうが価値がある。が、後者の方が安いはず。買うなら前者をすすめる。 |
|
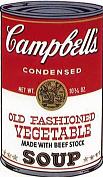
ウォーホール「キャンベル缶」(部分)
クリックするとウォーホール美術館に
入れます |
1950〜1970年頃
ポップアート:
第二次大戦後、美術の中心はパリからニューヨークに移った。そこで登場してきたのが、有名なこのポップアート。誰もが目にするマスイメージを芸術に置き換えた。知っておきたい人は数名いるが、今回は代表的なこの人。
アンディ・ウォーホール
従来の歴史的絵画とは全く異なる絵です。「絵って分かりません」と言われるのは、この人あたりから。 |
<物足りない人のために・・・>
ウォーホールはシルクスクリーン技法で版画をたくさん作った。それらは、今日でも数こそ少ないが売られている。しかしながら、真贋のはっきりしないもの、あとから刷り増しした「海賊版」も中にはある。ウォーホールは決して安くないし、ものによっては「投資」となる作品もある。購入する時には、慎重に来歴などを画廊からヒアリングする必要がある。サインもシートの裏側にあったりする場合もあるので、よく見せてもらうことが肝心。個人間売買で買おうとするのは危険。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
|